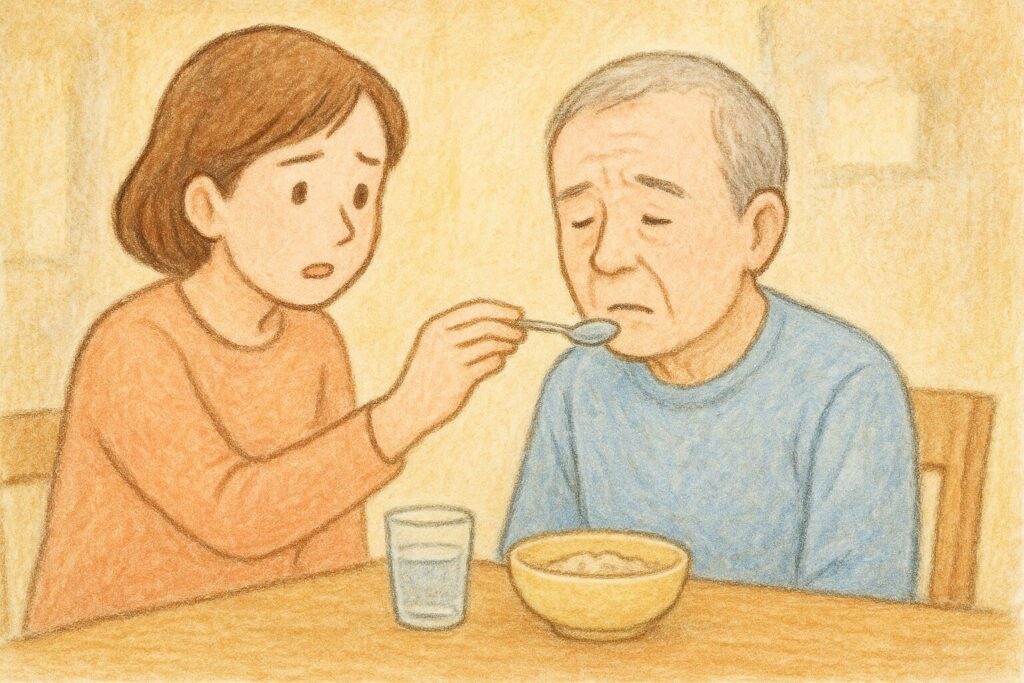
「口を開けてくれなくなってきた」
「ごはんを食べなくなってきた…」
現場では「食事拒否」と呼ばれることがありますが、
多くは“わざとではない”行動です。
デイサービスでも、訪問看護でも
「朝ごはん、まだ食べていないそうです」という方もしばしば。
そうなると個別に対応して食事、内服の手助けをしていきます。
背景には、次のような要因が重なります。
・食欲の低下/味覚の変化
・飲み込みづらさ(嚥下機能の低下)
・口腔失行(うまく口が開けられない・動かせない)
・注意の分散や不安、入れ歯や口内トラブル、薬の影響 など
この前提を共有すると、関わり方がやさしく、実用的になります。
本記事は「認知症 食事拒否/ごはんを食べない」場面で、
今日から試せる工夫を、お伝えします。
この記事でわかること
- 「食事拒否」が起きる背景と本当の理由
- 食欲を引き出すための軽い刺激の工夫
- 穏やかな環境づくりと声かけの工夫
- 楽しい食卓の雰囲気づくりのコツ
- 受診を検討するタイミングとサイン
軽い刺激:冷たいものを唇につけて刺激する

共感パート
「食事の時に口を開けてくれなくなってきた」──そんな声をよく耳にします。無理に食べさせようとしてもうまくいかず、介護する側も不安や焦りを感じるものです。
ポイントと理由
そのような場面では、冷たいもので口に軽い刺激を与える方法が役立ちます。口の周りや唇は温度に敏感で、冷たさに反応して自然に口が動くことがあります。これは生理的な反射に近く、無理のないきっかけづくりになります。
具体例
- スプーンに冷たい水を少量すくい、唇にそっと触れさせる
- 驚いたように口が開き、そのまま一口につながることがある
- 冷たい麦茶やゼリーなどでも同じ工夫ができます
まとめと促し
強引に食べさせようとするよりも、まずは冷たさで軽くスイッチを入れる。そんな小さな工夫が、安心して食事を進める一歩になります。
“穏やかな環境”に

ポイント:環境を整えるだけで、“食べない”は減ります
口を開けない・飲み込まない背景には、不安や集中しづらさもあります。 静かで落ち着いた場は、それだけで“食べる準備”になります。
理由:注意が分散すると、食事の目的がぼやける
認知症では同時に複数の刺激を処理するのが難しくなります。 テレビの音、会話、匂いが重なると「今は食べる時間」が伝わりません。
具体例:今日からできる環境づくり
- テレビ・ラジオはオフ。
- 食卓の上は最小限(茶碗・汁物・主菜を三角に配置)。
- 席は一定の場所に固定。デイサービスで毎回席が異なっても多くの方は大丈夫ですが、見える風景が同じだと安心する様です。
- 声掛けを“敢えてしない時間”も有効。
そっと座って同じものを一口食べ、見本を示します。 - 香りの強い柔軟剤・アロマは控えめ。 食事の匂いと混ざると負担が増えやすいです。
- 目の前に食事以外置かない。症状が進行すると、目の前のもの(ティッシュー等)なんでも口にしてしまうことも。
環境づくりのよくある質問
Q:食卓で付き添う人数は?
A:多すぎると緊張します。 1〜2名までが目安です。
Q:音楽は流しても良い?
A:歌いたくなる曲は注意。 インストゥルメンタルを小さめに。
Q:食べないとき、何分待つ?
A:5〜10分を上限にいったん場をリセット。 再挑戦は時間をずらして。
まとめ:静けさと見本で“今は食べる”を伝える
認知症 食事拒否の土台は、静かな場づくりです。 声よりも“見せる”が効きます。
“好き”を合図
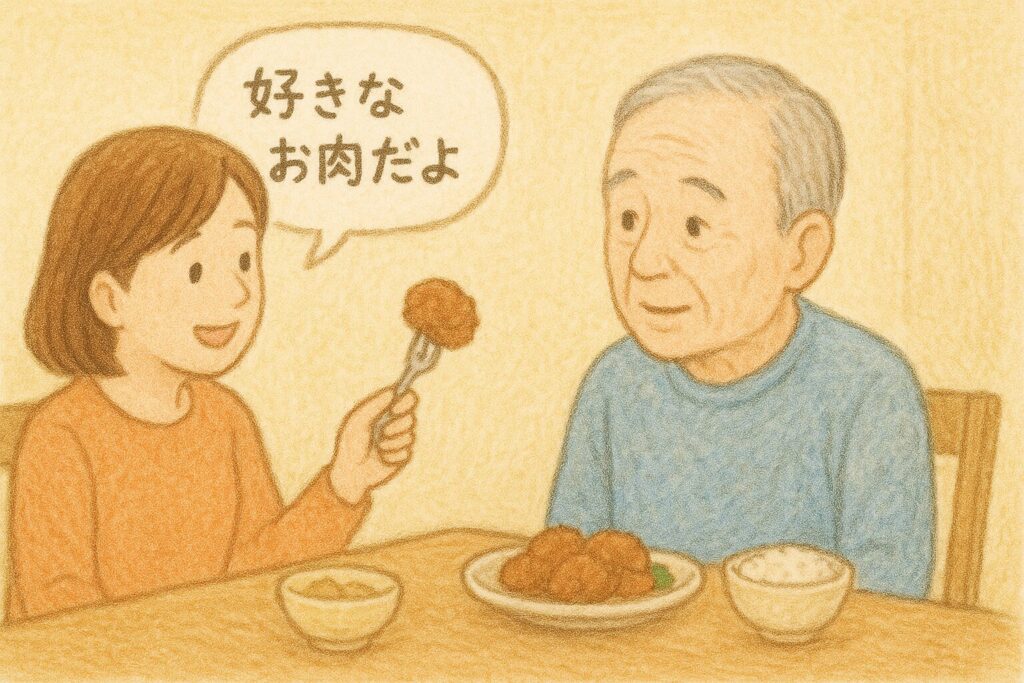
ポイント:短い肯定の声かけが、“食べない気持ち”をほぐす
「食べましょう」よりも、「好きな卵焼きだよ」のほうが届きます。 言葉は短く、笑顔で、指示は一度だけ。
理由:“好き”は感情の記憶に届きやすい
認知症では意味の処理が難しくても、感情の記憶は保たれやすいです。 “好き”の言葉は安心に直結します。
具体例:伝え方いろいろ
- 「好きな○○だよ」 → 一拍おいて → 皿を本人の手前へ。
- 「温かいお味噌汁だよ」 → 湯気をそっと見せる。
- 「今はごはんの時間だよ」 → 時計を指差し視覚で補う。
- NG例:「食べないとダメ」「ちゃんとして」などの否定語。
まとめ:短く、肯定的に、1回で伝える
認知症 食事拒否での声かけは、 短く、ポジティブな言葉で。
“つられ食べ”の力・・・楽しめる雰囲気で感情から食欲を引き出す

ポイント:人は“楽しい場”につられて食べます
楽しいと、つられて自分も笑顔になってしまうように
同じメニューでも、雰囲気で手の伸び方が変わります。
“食べない日”が続くときこそ、楽しい会話や笑顔を先につくります。
理由:感情は食行動のアクセルになる
楽しい・安心は、食べる動作の背中を押します。
具体例:“つられ食べ”を起こす工夫
家族も同じ時間に着席。
先に美味しそうに一口食べて見せる。
おしゃべりは食事と関係ある明るい話題。
「今日の味噌汁、香りいいね」など。

自分で食べるって大事です。
手に持ちやすいものを少量ずつ。
小さなおにぎり(持ちやすい俵形がオススメ)やパン、サンドイッチ、など。
「スプーンをここに置いてくれる?」「お皿を並べてくれる?」など、
デイサービスでもそうですが、役割があると満足した表情になります。
まとめ:理屈より、楽しい空気をつくる
認知症 食事拒否の日こそ、笑顔の演出を。
“つられて一口”が入れば、流れが変わります。
行動を促す一言:「おいしいね」と笑顔で伝えてみましょう。
安全上の注意と“受診の目安”——むせ・体重減少・脱水サインを見逃さない

ポイント:安全の確認は最優先
対応しても食べない、むせが増える、体重が急に減るときは、専門職に相談を。
理由:嚥下機能の低下や体調変化が隠れていることがある
誤嚥性肺炎や便秘、口腔トラブル、薬の副作用が関与する場合もあります。
具体例:相談・受診の目安
- 熱や咳・痰、強いむせが出る。
- 1〜2週間で2〜3kgの体重減少がある。
- 水分摂取が1日500ml以下が続く。
- 口内炎・合わない入れ歯が痛そう。
- 新しい薬の開始直後から食べない。
まとめ:対応+安全確認がセット
在宅なら訪問看護、主治医、言語聴覚士(ST)、歯科に早めの相談を。
行動を促す一言:体重と水分量を今日からメモ。
変化があれば、早めに相談しましょう。
まとめ|今日からできる“3つの一歩”
- 軽い刺激:冷たいスプーンで唇をタッチし、成功で終える。
- 穏やかな環境:テレビを消し、見本を示して“今は食べる”を伝える。
- 短い肯定の声かけ&楽しい雰囲気:「好きな○○だよ」。
つられ食べを誘う。
認知症 食事拒否に万能薬はありません。
でも、小さな工夫の積み重ねで“食べない日”は確実に減らせます。
今日の食事で、できることをひとつだけ試してみましょう。







コメント