健康のために毎日長距離を歩いていた
一人暮らしで認知症が始まっていたものの、身なりもきちんとしていて、足取りもまだしっかりしていた頃のある女性の話です。 毎日、2km、3km、それ以上の距離を歩くのが日課になっていました。それもサンダルで。
ご本人は 「健康のため」と信じて疑わず、家族がいくら心配しても聞き入れてくれませんでした。

何度かの転倒、そしてついに救急搬送
けれどある日、スーパーの前で転倒してしまい、救急車で搬送されることに。
数日前にも転んで顔面を強打したばかり。
この時は救急車を呼ぶ、呼ばないの大騒ぎに。その後、家族は悩み抜いた末に、施設への入所を決断しました。
“元気そうに見えても”認知機能の低下は進んでいた
元気に歩いている姿からは想像できないほど、認知機能は確実に低下していました。 本人の意志と安全のバランスを取ることの 難しさを痛感した出来事でした。
「ひとり歩き」は徘徊?それとも大切な日課?
「徘徊」とひとことで言っても、認知症のある方にとっては“理由のある行動”であることがほとんどです。家にじっとしていられず歩き出すのは、何か目的があったからかもしれません。けれど、それを本人に聞いても、「忘れた」「なんとなく」と返ってくることも多く、真実はわからないままです。
疲れを知らず、どこまでも歩けてしまう
認知症が進行すると、「疲れた」「痛い」 「危ない」といった身体のサインが感じにくくなっていくことがあります。歩き疲れることもなく、休憩もせず、目的地のないままに何kmも歩いてしまう方もいます。実際に、顔を強く打ってアザだらけなのに、本人は何事もなかったかのようにデイサービスに来所した…そんなケースもありました。

引き返すことは少なく、どんどん進んでしまう
また、迷ってしまったとしても、自分から道をたずねることは少ない傾向があります。「知らない人に話しかけるのは恥ずかしい」「迷ったことを認めたくない」そんな羞恥心や不安から、ますます先へ先へと進んでしまいがちです。
どこへ行こうとしていたのか?それは本人にも分からない
「どこへ行くつもりだったんですか?」と聞いても、明確な答えは返ってこないことがほとんどです。
でもきっと、何かきっかけや思いがあって歩き出したのでしょう。過去の思い出や習慣に基づいていることが多いようです。例えば、長年会社に行くために通った道、食事の支度のために買い物に出かけていた商店街など。たとえ理由が分からなくても、「徘徊=問題行動」と決めつけず、その人なりの理由や生活の流れを大切に見ていくことが必要です。
姿が見えなくなったら、まずすべきこと
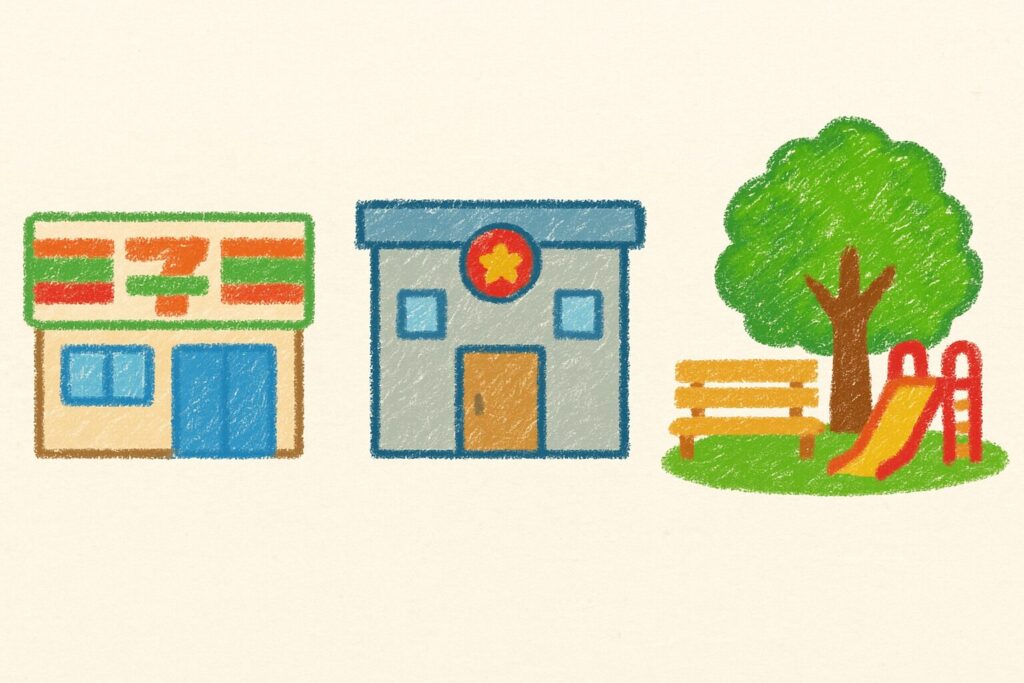
万が一、姿が見えなくなってしまったときには、闇雲に探すのではなく、「立ち寄りやすい場所」に目を向けてみましょう。たとえば、近くのコンビニ、交番、公園、バス停など、少しでも目撃情報が得られそうな場所を優先的に確認するのが効果的です。また、早めに*「認知症SOSネットワーク」などを活用して、地域に協力を求めることも大切です。
*「認知症SOSネットワーク」とは
事前に、名前や連絡先、身体の特徴等を登録しておくこと
お住まいの市区町村にお問合せをしてみてください
安心して歩いてもらうために家族ができること
「もう外出しないで」「歩くのをやめて」と止めることは簡単です。けれど、そうした声かけが本人の不安や混乱を強めてしまうこともあります。歩き出す気持ちには、“何かを探している”“誰かに会いに行こうとした”といった理由があるかもしれません。
大切なのは、「歩くことをやめさせる」のではなく、「安心して歩けるようにする」視点です。家族ができる工夫をいくつかご紹介します。
名前入りの靴や衣類は、“命綱”になる
実際に、道に迷って立ち尽くしていた方が、履いていた靴に書かれた名前を見た通行人の機転で、家族に連絡が入ったケースがありました。一見地味な工夫ですが、名前や連絡先を記した持ち物は、命を守る手がかりになります。衣類のタグや帽子、杖、カバンなどにも記名しておくと安心です。
いつも持ち歩くカバンがあればそれに名札を取り付けたり、上着に名前シールを貼るのも良いでしょう
肌に優しく、洗濯や乾燥機でも剥がれないお名前シールはこちら
徘徊対策 認知症対策 布シール 20×50mm [ 名前 + 住所 + 電話 ] 名前シール お名前シール アイロン 布用
GPS付きの見守りグッズを活用する
「どこにいるか分からない」が一番の不安です。最近では、靴にGPSを内蔵したタイプや、キーホルダー型・見守り用スマホなど、高齢者向けの位置確認ツールが充実しています。
費用は月額500円〜1,500円程度が多く、 見守りサービスと連携しているものもあります。手が震える、ボタンが押せない方でも使いやすいシンプルなものを選ぶのがポイントです。
どこにいるか分からない不安に備えるために、履きなれた靴に取り付けられるGPSアイテムも便利です。
地域の支援制度を活用する
自治体によっては「認知症高齢者見守りSOSネットワーク」や「事前登録制度」などがあり、外出して行方がわからなくなった場合に、警察や地域住民、商店街と連携して迅速に保護につなげる仕組みがあります。
事前に登録しておくと、早期発見や保護の確率がぐっと高まります。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談して、地域の制度を確認しておくと安心です。
「歩かないで」ではなく、「一緒に歩こうか?」

本人の自立心を尊重しつつ、行動の安全を見守る方法もあります。たとえば、決まった時間に一緒に散歩することで、本人の外出欲求を満たしつつ、安心して歩いてもらえます。
また、「この道だけならOK」「ここに行く時は連絡してね」といったルールづくりも、本人の尊厳を保ちながらリスクを下げる方法のひとつです。
まとめ:“歩く自由”と“安心”のあいだで、できることを探していく
認知症の方の“ひとり歩き”は、決して「問題行動」ではありません。そこには、その人なりの思い、日々の習慣、不安やこだわりといった背景があります。
でも、家族にとっては「無事に帰ってこられるだろうか」という心配が常につきまといます。 「歩かないで」と言いたくなる気持ちは、愛情ゆえの自然な反応です。
けれど、その人らしさを大切にしながら、安心も安全も守る方法はきっとあります。名前入りの服、GPS、地域の支援制度――小さな工夫が、安心と自由の橋渡しになります。
「歩かないで」と制限するよりも、「どうしたら安全に歩けるか」を一緒に考えていけたら。そんな視点が、介護する人もされる人も、少しラクになる一歩につながるのかもしれません。







コメント