- 自宅なのにウロウロしているなと思ったら、トイレに行こうとしていた
- 頻回にトイレに行くけれど、転ばないか心配で付き添っていたら、自分の睡眠不足が続く
- 充分に拭けずに下着を汚してしまう
排泄に関する悩みは本当に多く、でも人にはなかなか相談しにくいもの。
つい怒ってしまって後悔したり、我慢の限界を感じてしまうこともあるでしょう。
今回は、認知症の方が「トイレの場所がわからなくなる」問題に焦点を当て、
家庭でできる工夫や声かけの方法を現場で経験した看護師の視点でまとめました。
記事を読んだ後に
・今からできそうなことがわかる
・気持ちが軽くなる
と嬉しいです。
なぜトイレの場所がわからなくなるのか?

認知症が進むと、こんなことが起こります。
・「今、自分がどこにいるのか」がわからない
・「これから何をしようとしていたのか」を忘れる
これは“見当識障害(けんとうしきしょうがい)”と呼ばれ、
時間や場所、人の区別がつきにくくなる症状の一つです。
たとえ自宅であっても、「ここはどこ?」 「トイレはどこ?」と混乱してしまい、
部屋の中をウロウロしてしまうのです。
他にも起こること
・記憶障害によって「トイレに行きたい」という感覚を忘れる
・排泄動作そのもの(ズボンを下ろす、座る、拭くなど)がうまくできない
・「何度もトイレに行こうとするけれど、たどり着けない」
・「違う場所で排泄してしまう」
家庭でできるトイレ誘導の工夫と声かけ
無理に誘導せず、本人の気持ちを尊重した声かけと環境づくりが大切です。
「トイレに行きたいのかな?」と思っても、どんなふうに声をかけていいか迷う場面は多いものです。無理に誘導すると嫌がられることもあるため、自然な形で声をかけ、行動を促す工夫が大切です。

排泄のタイミングを知っておく
まずは、日々の観察から本人の排尿・排便のパターンを把握しましょう。
- 「朝食後に多い」
- 「昼寝のあとが多い」
ある程度のタイミングがわかれば、 声かけがしやすくなります。
記録のメリット - タイミングが予測しやすくなる
- ケアマネや医師への相談材料になる
- 介護保険サービスの見直しに役立つ
簡単なメモでOKです。時間と「成功・失敗」を記録するだけでも十分です。
男性の場合は、早めに座って排尿する習慣をつけておくと、後が楽です。
デイサービスなどでは座ってお願いされることが多いです。
声かけのコツは「さりげなく・共感的に」
認知症の方は、「自分でできる」と思っていることが多いため、
命令的な声かけや強制的な態度は逆効果になることがあります。
良い例:
- 「一緒に行こうか?私も行きたいし」
- 「寝る前に行っておきましょうか」
相手のペースを尊重するといいですね。
トイレの回数を増やす(膀胱トレーニング)
デイサービスでは「おむつを汚す回数が少ない」と言われることがあります。
これは
「トイレに行く習慣をつける」からです
✔ 食事の後・寝る前など、決まったタイミングでトイレに行く
✔ 「そろそろトイレの時間ですよ」と声かけをする
「出ないよ」と言われても、実際に行ってみると排泄があることも少なくありません😊
おむつ=介護ではなく「安心パンツ」と伝える
「おむつ」という言葉に強い抵抗感を持つ方も多いので、言い方を工夫しましょう。
- 「安心パンツ」
- 「リハビリパンツ」
夜間は吸収量の多いタイプに変える、パッドを利用する、ギャザーをしっかり立てるなど、
小さな工夫も効果的です。
トイレの場所がすぐわかる環境づくり
トイレの場所をわかりやすくしておくことは、失敗を防ぐ第一歩です。
■ 見た目で「トイレらしさ」を伝える

- 「便所」「トイレ」などの表示を大きく貼っておく
(大きめの字で、目線の高さにすることも大事なポイントです) - ドアを少し開けておく/中が見えるようにする
- トイレのフタはあけておき、ブルーレットなどの色つき洗浄剤で“ここが排泄の場所”とわかりやすくする
■ 誘導サインや照明の工夫
- 廊下に矢印表示や写真などを貼っておく
- 夜間はセンサーライトで足元を照らす、またはトイレの電気をつけたままにしておく
- テープなどを使って“トイレまでの道”を視覚的にわかりやすくする
「見てすぐにわかる」工夫は、認知症の方にとってとても大切です。
着脱しやすい服装への変更
ポイント:
- ゴムウエストのズボン
- マジックテープ式の衣類
- ワンピースより上下分かれた服
着脱に時間がかかると、間に合わないことが増えます。
ポータブルトイレの検討
こんな場合に有効:
- 夜間のトイレ移動が危険
- トイレまでの距離が遠い
- 介護者の睡眠確保が必要
お部屋の中にトイレを置くってとても抵抗があると思います。
最初は抵抗があっても、慣れれば安全性が高まります。
トイレの底にペットシーツを敷くと音の軽減や処理が簡単になります。
医療的な相談も視野に
相談すべきケース:
- 頻尿がひどくなった
- 尿意を感じにくくなった
- 便秘や下痢が続く
泌尿器科や消化器科で相談すると、改善できることもあります。
トイレ以外で排泄してしまったときの対処法
基本姿勢:叱らない・責めない
最初はショックを受けますよね。
でも、これは本人の意思ではなく、認知症による混乱です。
声かけの例:
- 「大丈夫だよ」
- 「一緒に工夫していこうね」
淡々と対応するとスムーズです。
感情が爆発しても自分を責めすぎない
現実には、嫌な顔をしてしまうこともあります。
「もういい加減にして…」と言ってしまうこともあるでしょう。
でも、それは真剣に向き合っている証拠です。完璧な介護なんてできません。
感情があふれる日があって当然です。
汚れたときの備えをしておく
- ジョイントマットやユニットカーペットで汚れた部分だけ洗えるようにする。
- 違う場所をすっかりトイレだと思い込んでいるときには、「小便禁止」と書いた張り紙や、ペットシーツを敷いておくといった対策も有効です。洗えるペットシーツは価格も手頃です。
- 汚れた下着を入れるバケツやビニール袋を目立つ場所に置き、本人が自分で入れられるようにする。
- 布団が汚れてしまうお悩みには防水シーツも役立ちます
外出時の対策
あらかじめトイレの場所を確認しておきましょう。
施設や大型の建物では、案内表示もチェックしておくと安心です。
家族の気持ちと在宅介護の限界
排泄の支援は、身体的な疲労だけでなく、心の疲れも大きく影響します。
夜間の対応や失敗の片づけが続くと、介護者の生活そのものが成り立たなくなることもあります。
実際には、夜間に2時間おきに起きてトイレに付き添うようになると、介護者の睡眠が不足し、日中の仕事に支障をきたすケースが多く見られます。
「このままでは無理かも」と思ったときは、外部の支援を取り入れるタイミングかもしれません。
- ケアマネに相談
- デイサービスやショートステイの利用
- 施設入所という選択肢も含めて検討する
「家族だけで頑張らない」こと、限界まで我慢しないことは
介護を続けていく上でとても大切な視点です。
まとめ:うまくいかない日があっても、それが普通
トイレのことは、想像以上に心を揺さぶられます。 「怒りたくないのに、怒ってしまった」
「自分ばかり頑張っている気がする」 そんな気持ちになるのも、介護を真剣に続けてきたからこそ。
でも、介護はうまくいかない日もある、それが普通です。
「大丈夫じゃない」と思ったら、どうか声をあげてください。
頼れるところに頼って、自分を少しでも楽にしてあげてください。
ご自身の人生も大切にしてほしいと思います。
今日できたことを、どうか自分で認めてあげてくださいね。
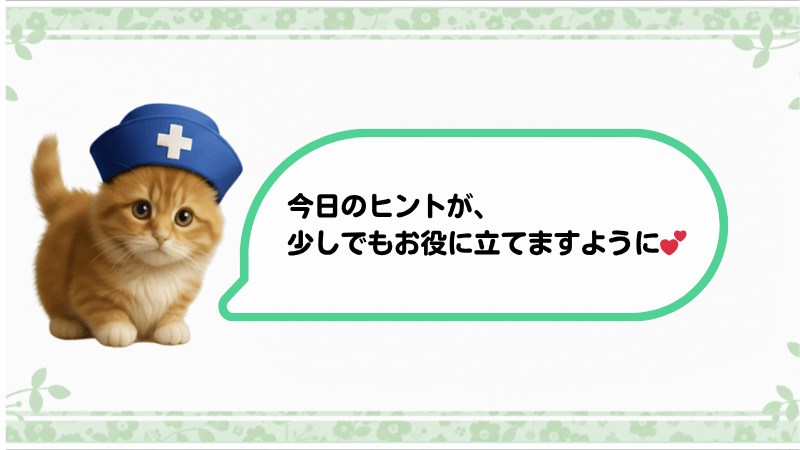




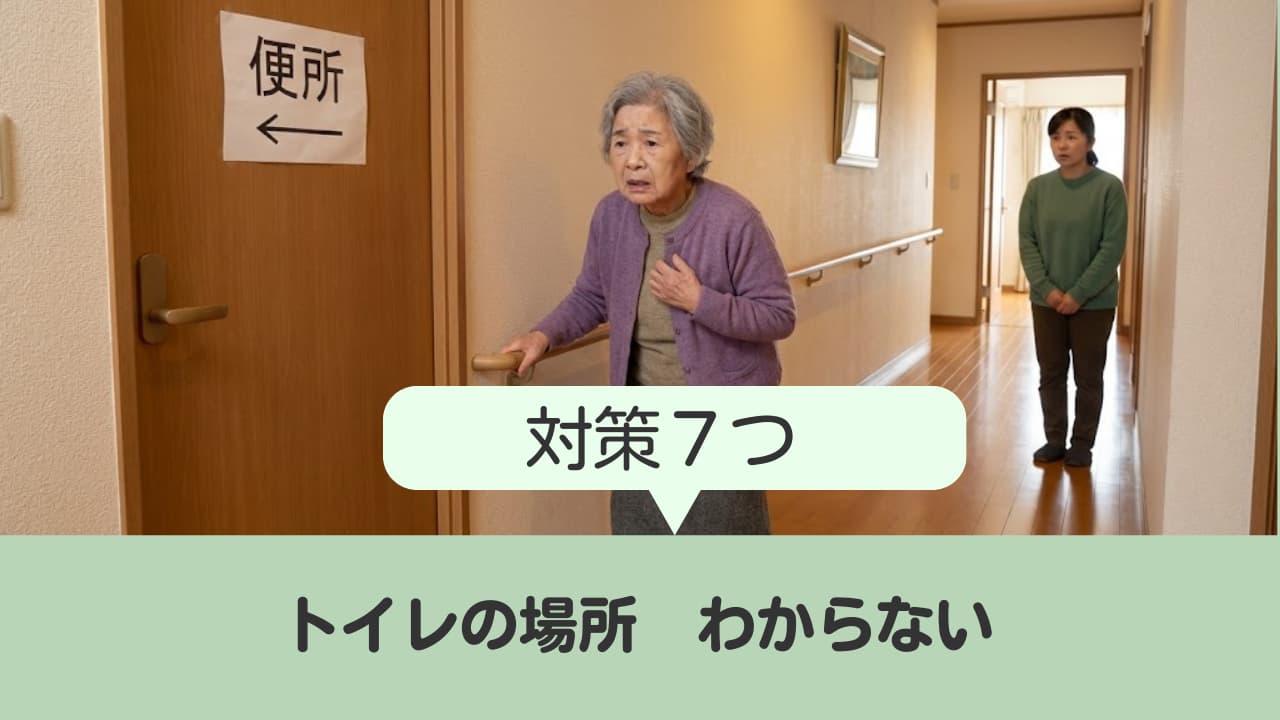


コメント