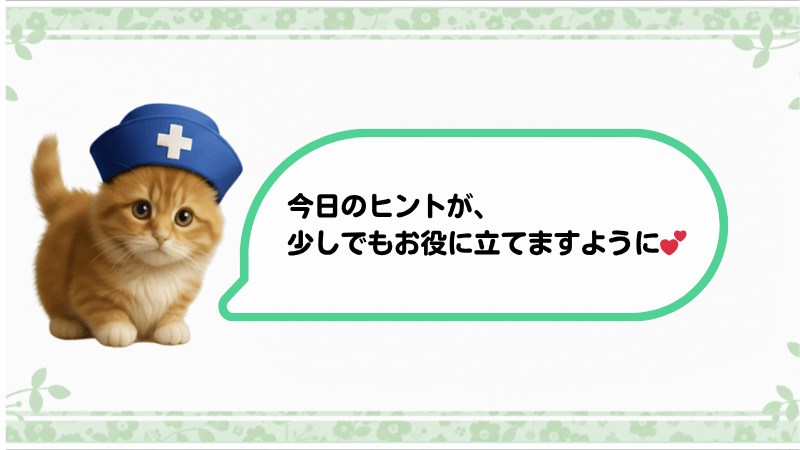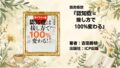介護をしていると「前より飲み込みにくくなってきたな」と感じることがあります。
たとえば、以前は普通に食べられていたのに、最近になって
水分でむせやすい
しゃべらなくなってきた
いつまでも口の中でもぐもぐしている …。
そんな変化に気づいたら、ちょっと注意したいサインです。
飲み込む力が弱ってくると、誤嚥性肺炎のリスクも高まりますものね。

誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)とは 食べ物や飲み物、あるいは唾液(つばのこと)などが誤って気管(空気の通り道)に入り、 肺で炎症を起こす病気
実は、飲み込みにくさには
年齢や筋力の低下、口の中の乾燥、入れ歯の不具合 など、いくつか理由があります。
でも――ここで大事なのは “原因探しより、できる工夫”。
気づいたところから小さな工夫を積み上げていけば、食べる楽しみはちゃんと守れます。
だからこそ、「できなくなった」と思う前に
“どう続けていくか” に気持ちを切り替えていくことが大切です。
今回は、そんなときに試しやすい工夫をご紹介しますね。
飲み込みにくい時の対策
① おしゃべりをしよう

口や舌を動かすことは、実は嚥下のトレーニングになります。
食事の前に「今日は何食べようか?」なんて会話をしたり、思い出話を一緒にするのも効果的。
楽しい気持ちがふくらめば、自然と口もよく動きます。
でも、現実はなかなか会話は弾まない時も多いですよね😢
最近目にする機会が増えたAIロボット。
お子さんからのプレゼントでおしゃべりできるぬいぐるみといつも
他愛のない会話を楽しんでいるご利用者さんがいます。
認知症のその方はヘルパーさんとも会話はされないのに、このぬいぐるみには
優しい表情で声をかけていらしたのが印象的でした。
肌触りもよく、抱き心地も⭕️ 話しかけると答えてくれるのでおしゃべりが弾むみたい。
笑顔がみられるようになるとこちらも微笑ましくなります😃
② 食前にひと口の水分
食事を始める前に、水やお茶をひと口飲んで喉を潤しましょう。
潤いがあると飲み込みやすく、むせ予防にもなります。
さらに「ごくん」と飲むこと自体が、嚥下を思い出すきっかけになり、食事のリズムが取りやすくなります。
③ 「ごっくん」と声かけ
そばについているとき、飲み込む瞬間に「ごっくん」と優しく声をかけてみましょう。
ちょっとした合図になるだけで、安心して飲み込みやすくなります。
「大丈夫だよ」という気持ちを込めて声をかけることがポイントです。
④ 自分で食べることを応援
むせたり時間がかかったりすると、つい介助してあげたくなりますよね。
でも、自分で食べる力はとても大切。
一口でも自分で口に運べると、「まだ食べられるんだ」という自信にもつながります。
疲れてしまったら、1日3回にこだわらず、小分けにして食べてもOK。無理のないペースで応援してあげましょう。
⑤ 食器を工夫する
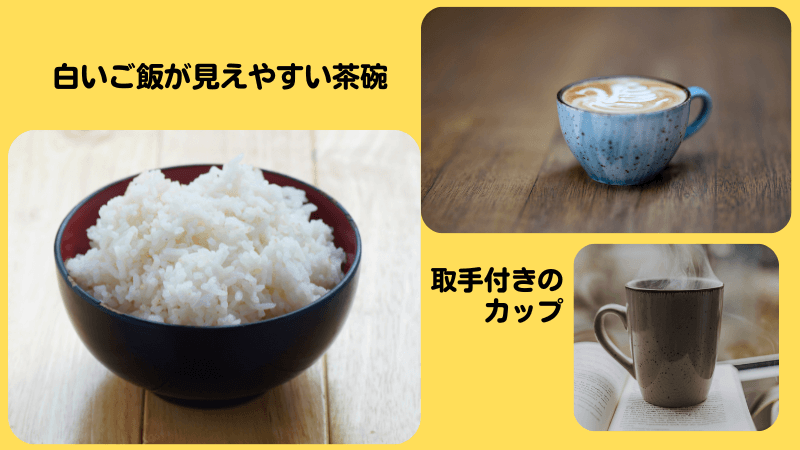
「食べやすい」って、環境の工夫でも変わります。
- 白いご飯が見えやすい色のお茶碗
- 持ちやすい取手付きのカップ
ちょっとした工夫でも食事が進んで、笑顔が増えることがあります。
⑥ 市販の介護食をうまく利用しよう
介護の食事づくりって、毎日のことだから本当に大変ですよね。
私も母を介護していたとき、最初は「できるだけ手作りで」と思って、ペースト食をミキサーにかけたり工夫していました。
でも、気づけば一日中、食事の準備と介助に追われてクタクタに…。
そんなときに助けてくれたのが、市販の介護食でした。
「舌でつぶせる」「かまなくてよい」など、食べる力に合わせて選べるので、とても心強い味方になります。
入れ歯が合わなくなったときや、内臓のご病気があるとき、さらには災害時の備えとしても役立ちます。
たとえば キユーピーの『やさしい献立』シリーズ は種類も豊富で、家族と同じように温かい食事を楽しめる工夫がされています。
「全部を手作りしなきゃ」と頑張りすぎず、こうした介護食を上手に取り入れることで、介護する人の心と体も少し軽くなりますよ。
まとめ

飲み込みにくさは、誰にでも起こりうる自然な変化です。
でも、ちょっとした工夫と見守りで「食べる楽しみ」を続けることができます。
そして何よりも、食事は毎日のこと。介助する人にとっても大きな負担になりがちです。
「全部やらなきゃ」と思うと疲れてしまいますから、できる工夫を少しずつ取り入れて、無理せずに続けていきましょう。
大切なのは、本人も介護する人も「できることを一緒に探していこう」という気持ち。
根気はいりますが、その積み重ねが安心や笑顔につながります。
食卓で「今日も一緒に食べられたね」とほっとできる時間を、どうか大切にしてください✨