デイサービスでよく聞く言葉のひとつに、
「さあ、もうおいとまいたします。家に帰ります」というセリフがあります。初めての来所時や、昼食後によく見られる場面です。
ご家族からも
「自宅にいるのに『家に帰りたい』と言うんです」と戸惑いの声を聞くことがあります。
では、いったいその“帰りたい家”とは、
どこなのでしょうか?
その人が「行きたい」「帰りたい」と
思っている場所とは?
帰りたい場所は“気持ちが安らぐ場所”

結論から言うと、帰りたい場所は
「気持ちが安らぎ、楽しいと思える場所や時間」であることが多いようです。
幼少期を過ごした故郷だったり、
日々の習慣だったスーパーへの買い物、
定時に通っていた会社など、
人によってさまざまです。
本人にとって、まるでタイムスリップするような感覚で「帰らなければ」と思うのです。
その一方で、「どこに行くの?」と尋ねられると、うまく答えられないこともあります。
「家に帰りたい」と言う3つの理由
① 本人にとっては“現実”
何か大事な用事があると感じているのに、
何だったかは思い出せない。
「出かけなきゃ」と思って外に出たけれど、
道を尋ねるのは恥ずかしい…。
そんな気持ちが迷子のような状態を招くことがあります。
② 自宅にいても“自宅”と感じられない
脳の認知機能の障害により、たとえ自宅にいても「ここは自分の家じゃない」と感じてしまうことがあります。
③ 不安から逃れたい気持ち
自分の状況がよくわからないとき、
いろいろな不安がわき起こってきます。
「安心できる場所に帰りたい」という思いが強くなるのは自然なことです。
これらの理由は一つだけではなく、いくつかが重なっていることも多いです。
対応のヒント(5つの対策)
① 言葉をそのまま受け取らず、まずは穏やかに話を聴く
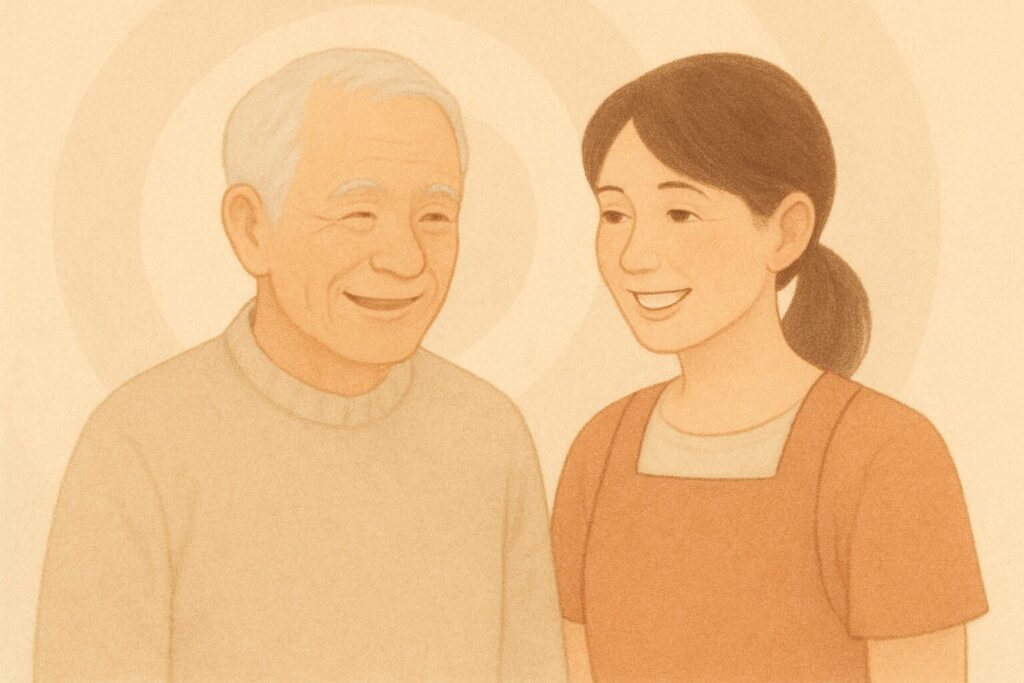
「帰りたい」という言葉の背景には、
不安や寂しさ、生活リズムの感覚など、
さまざまな思いが隠れています。
まずは焦らず、
その人の話に耳を傾けてみましょう。
② 寄り添う気持ちをもつ
「少し一緒にお話ししませんか」と隣に座るだけで、気持ちが落ち着く方もいます。
「子どもが帰ってくるからご飯の支度をしなくちゃ」と話す方が多いのは、家族への愛情が深いからこそ。
場所や時間よりも、
“誰かと過ごした安心の記憶”に帰りたいのかもしれませんね。
③「今、車を手配しますね」など具体的な言葉で一時的に安心させる
「帰りたい」という訴えに対し、
「わかりました、今手配しますので、少しだけ待っていてくださいね」と伝えると落ち着く方もいます。
“気持ちを受け止めてもらえた”と感じることが安心につながるのです。
④ 他のことへ気持ちを向けてみる

夕方に強く訴えが出ることが多いのは、
いわゆる「夕暮れ症候群」の影響かもしれません。
暗くなると「帰らなきゃ」という本能的な感覚が働くのです。
そんなときは、おやつの時間や軽いレクリエーションなど、自然に気持ちを切り替える活動を取り入れてみましょう。
⑤ 一緒に外へ出てみる
時間や人手に余裕があれば、少し外に出て一緒に歩くだけでも気分転換になります。
外の空気を吸いながら話すことで、
「自分は大丈夫」という感覚が戻ってくることもあります。
まとめ:その人にとっての「安心できる場所」を探して
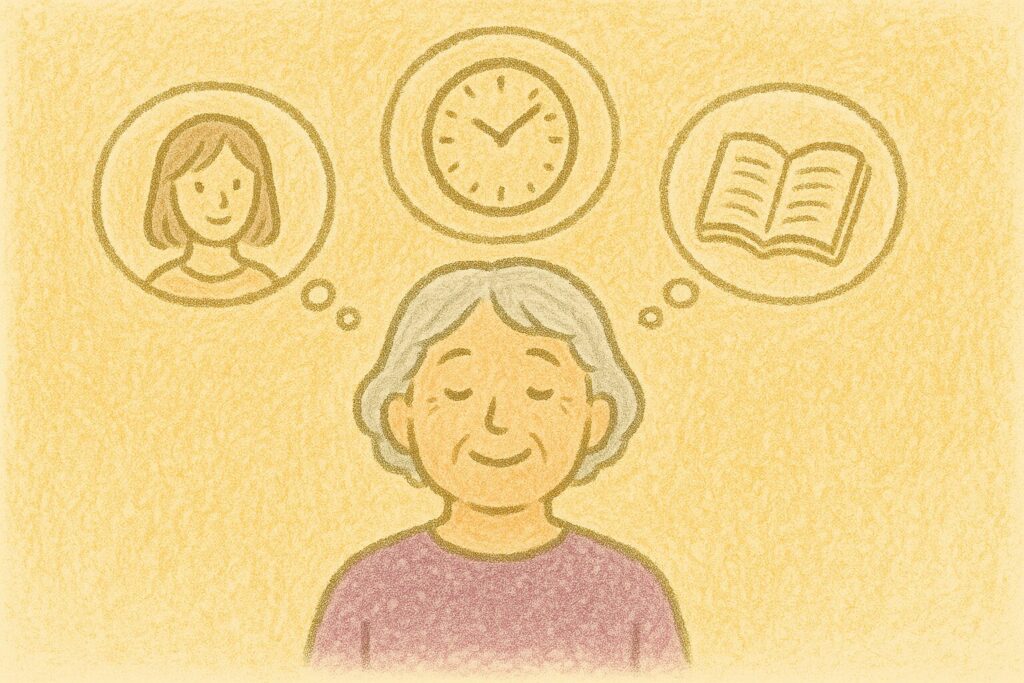
「家に帰りたい」という言葉には、
現実の住居以上に、“心のよりどころ”が込められているように感じます。
その背景には、かつて大切にしていた人、習慣、時間の流れなどがあるのかもしれません。
だからこそ、介護する私たちは
「どこに帰りたいのか?」ではなく、
「何がその方にとっての安心なのか?」
を見つめていくことが大切です。




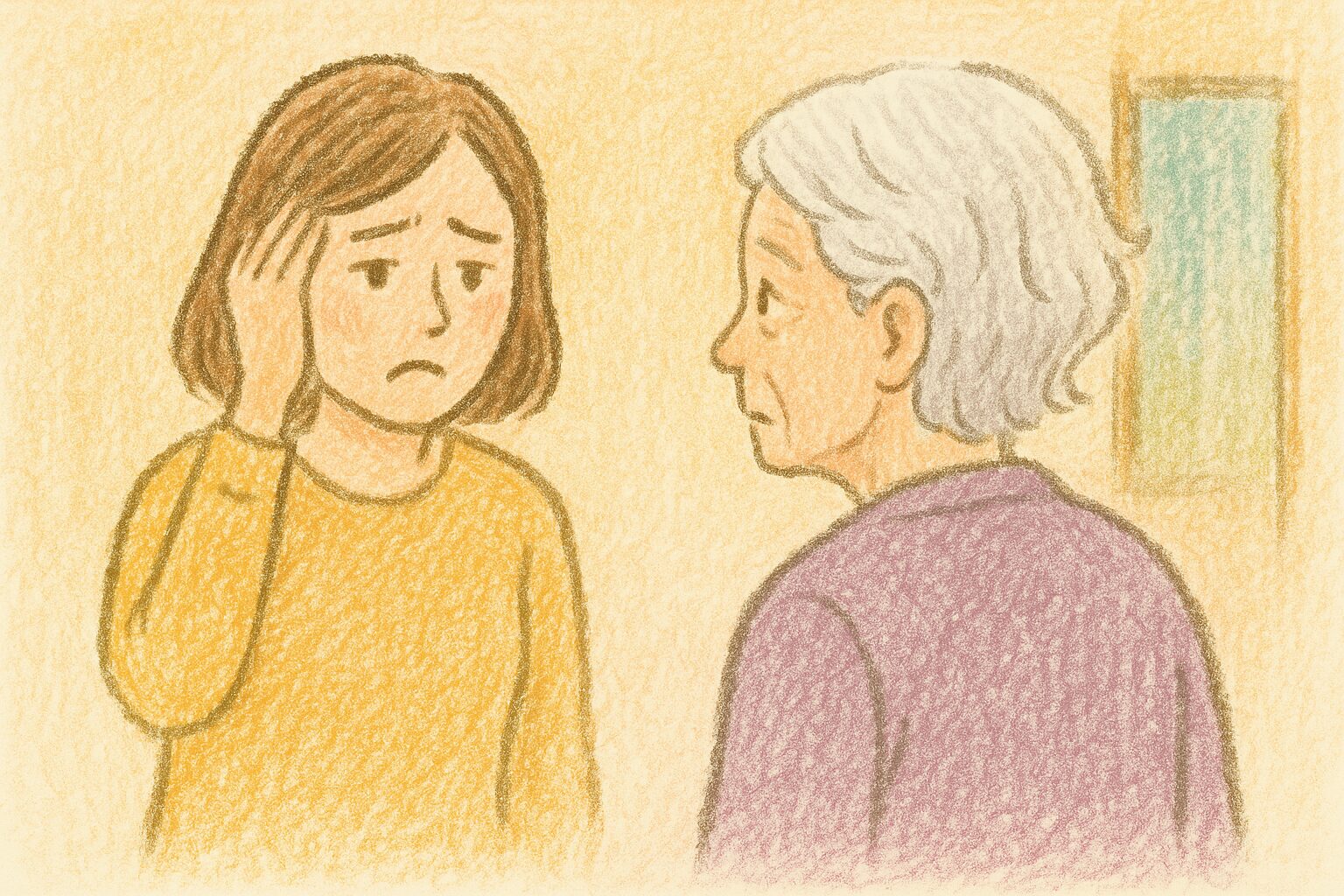


コメント