
「さっき食べたでしょ?」――ついそう返したくなる瞬間、ありますよね。
忙しい朝に何度も「ご飯は?」と聞かれると、優しくしたいのについイライラ。
そして…あとで自己嫌悪💦
この繰り返しに悩んでいませんか?
その言葉の裏には、記憶の問題だけでなく
- 「なんだか不安」
- 「気持ちを受け止めて」
- 「話を聞いてほしい」そんなサインが隠れています。
この記事では、看護師として認知症ケアに長年携わってきた経験から、
「心」と「身体」の両面に寄り添う対応法をまとめました。
読み終わる頃には、
今よりちょっと肩の力が抜ける“ちょうどいい距離感”がきっと見つかります。
まず確認!繰り返しの訴えは「身体のサイン」かも
繰り返しの訴えというと、「ご飯は?」の他にも
「トイレに行きたい」、「今日は何曜日?」などがありますよね。
じつは 「せん妄」や「脱水」「薬の影響」 など身体の不調から来ていることも。

せん妄って?

環境の変化(ショートステイ後など)や感染症で出やすく、
ぼんやり・興奮・夜間の混乱などが突然見られる症状のことよ。
繰り返しの訴えが続く時は、
主治医や訪問看護師に相談を。
まず試したい3つのこと【チェックリスト】
身体の不調が考えにくい場合は、この順番で試してみましょう。
☑️ STEP1:気持ちを受け止める声かけ
□ 「さっき食べたよ」と穏やかに事実を伝える
□ 不安そうなら「食べてないように感じるんですね」と共感
□ 「ソワソワしてる?」と気持ちを言語化
所要時間:30秒〜1分
☑️ STEP2:一口おやつを渡す
□ 小分けのおせんべいやゼリーを用意
□ 「じゃあこれ食べようか」と渡す
□ 食べている間に少し話を聞く
所要時間:2〜3分
☑️ STEP3:食器を視界に残す
□ 食後すぐに片付けない
□ 本人の視界に入る場所に置く
□ 1〜2時間後に片付ける
所要時間:0分(片付けを遅らせるだけ)
認知症による食事忘れへの対応法5選
身体の不調が原因として考えにくい場合は、
次に “心のアプローチ” と “記憶・環境のアプローチ” を意識してみましょう。
ここからは、認知症の方が落ち着きやすくなる関わり方を5つ紹介します。
まずは気持ちを受け止める穏やかな声かけ(心のアプローチ)

基本の声かけ:
- 穏やかに「さっき食べたよ」と事実を伝える
- 不安そうなら「食べてないように感じるのですね」と気持ちを受け止める
特に効果的な場面:
- デイサービスの予定日
- ショートステイ前
- 環境変化がある時
声かけ例: 「ちょっとソワソワしてる?」「不安になっちゃったかな」
→ 気持ちを言語化するだけで落ち着く方が多いです。
一口おやつで安心感を(心のアプローチ)

「食べたい」は実は「安心したい」のサイン。
おすすめ:
- 塩分控えめの小分けおせんべい
- 飲み込みやすいゼリー(高カロリーゼリーなど)
- 一口サイズのおにぎり
ポイント:お腹より心の不安を満たすことが目的
少量の食事で満足感を(心と環境のアプローチ)
「じゃあ少し食べようか」と少量だけ用意。
コツ:
- 必ず少量にする(食べきってしまうため)
- 介護者の負担にならない範囲でOK
- ”満たされた感覚”が残ることが大切
食器を残して“視覚”で記憶をサポート(記憶/環境のアプローチ)

アルツハイマー型では短期記憶がうすれ、
言葉より 「見た情報」 が記憶のヒントになります。
具体策:食べ終わったお皿をすぐ片づけず残しておく。
自分のお皿や茶碗、箸を見ることで「ああ、食べたんだ」と納得されることがあります。
夜間の冷蔵庫ロックで安全を守る(環境アプローチ)
夜中に冷蔵庫を開けて大量に食べてしまう方向け🌀
対策:
- 家族不在時や夜間はチャイルドロックを使用
- 誤嚥や腹痛のリスクを減らせます
リビングにお茶や軽食を置いておく
夜間不眠でお悩みの方へ:
介護者も親御さんも安眠できる方法があります。 → 介護者も介護を受ける人も安眠できる!夜間不眠に効くアロマの使い方
NGな声かけ例【チェックリスト】
こんな言葉、使っていませんか?✓で確認してみましょう。
❌ 避けたい声かけ
□「さっき食べたでしょ!」(強い口調)
→ なぜNG?:責められていると感じて不安が増す
□ 「また?ちゃんと覚えてよ」
→ なぜNG?:記憶障害を責めても改善しない
□ 「認知症だから仕方ないね」
→ なぜNG?:本人のプライドを傷つける
□ 「嘘つかないで。絶対食べたよ」
→ なぜNG?:本人にとっては嘘ではなく真実
□ 「何回言ったらわかるの?」
→ なぜNG?:怒りが伝わり関係が悪化
□ 無視する・相手にしない
→ なぜNG?:不安が増幅し、訴えがエスカレート
⭕ OK な声かけ例
| NG例 | OK例 |
|---|---|
| 「さっき食べたでしょ!」 | 「30分前に一緒に食べたよね」 |
| 「また言ってる…」 | 「お腹空いた感じがするんだね」 |
| 「覚えてよ!」 | 「心配になっちゃったかな?」 |
| 「嘘つかないで」 | 「そう感じるんですね」 |
もっと深く学びたい方へ:
イラストでわかりやすく解説された一冊。 → 『認知症は接し方で100%変わる』読書感想
まとめ
「食べていない!」の裏には、
“不安” “寂しさ” “確かめたい気持ち” が潜んでいることが多いです。
同じ質問が続くと、心がすり減りますよね。
でも、
その言葉の裏にある“本当の気持ち”を少しだけ想像できると、
ケンカにならない距離感がつかめてきます。
大切なこと:
- 完璧を目指さない
- 今日できる範囲で関わる
- 必要な時は専門家に相談
がんばりすぎず、あなたらしいペースで介護していきましょう🌿
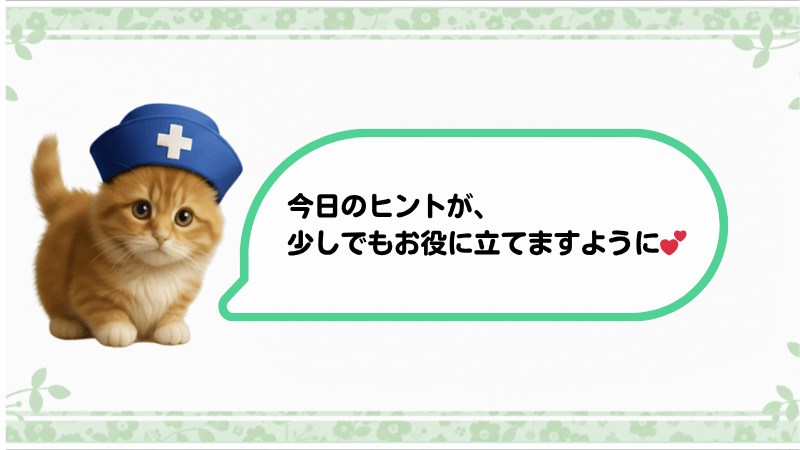







コメント